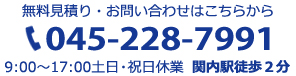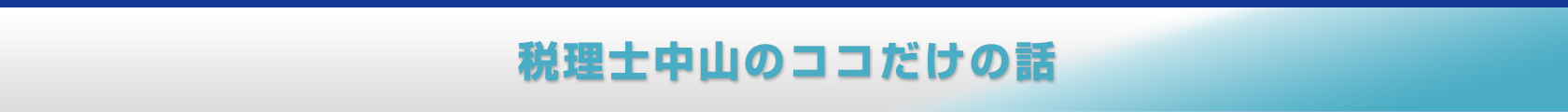買い物弱者の増加とその対策
「買い物弱者」と言う言葉を知っていますか?
買い物弱者とは、流通機能や交通網の弱体化とともに食料品等の日常の買物が困難な状況に置かれている人々をいいます。
買い物弱者の数は高齢者が多く暮らす過疎地や高度成長期に建てられた大規模団地等を中心に増加傾向にあり、経済産業省では、その数を700万人程度と推計しています。
経済産業省が公表している「買い物弱者応援マニュアル」によると、買い物弱者問 …もっと読む
退職後に前職の健康保険証を使用したら
退職等で前の会社の健康保険の資格がなくなった後は、すぐに再就職しなければ普通は国民健康保険に加入します。
その手続の前に旧保険証を使用して、医療機関を受診した時は、一旦協会けんぽ(健康保険組合の場合もあり)が立替えて病院へ支払いし、後日受診者から協会けんぽに負担分(総医療費の7割から8割)を返還する事になります。
◆返還手続
医療機関ではその保険証が有効か無効か判断できないため、医療機 …もっと読む
相続税の自主申告 国税庁 誤りやすい事例を公表
今年は相続税大増税元年と言うこともあり、弊事務所もたくさんの相談を受けました。
昨年と今年、亡くなる時期が違うだけで大きく税金が異なるので「節税したい!」という気持ちはわかりますが、過度な節税は税務調査で問題となることも多いです。
過日、国税庁は今後、専門家に頼らず相続人の自主申告が増えると予測してか、誤りやすい事例を公表しました。幾つか紹介をしてみたいと思います。
専 …もっと読む
「高齢者の地方移住」の支援へ 政府「住み替え税制」を検討中
◆家康の隠居先が「駿府」であった理由
関ケ原の戦いで西軍に勝利した徳川家康は、慶長10年(1605年)に将軍職を子の秀忠に譲った後、駿府(現在の静岡市)に隠居しました。
わざわざ「駿府」に隠居した理由については、家康が好んでいた富士山が見えて、鷹狩りの良い場所があり、好物の茄子(折戸茄子)があるからとも言われています(いくつかある「一富士二鷹三茄子」の由来の一つとなっています)。
もっと …もっと読む
実は優良パスポート? 日本のパスポート事情
年末年始を海外で過ごされる方も多いかと思いますが、今回は日本のパスポートについて考えてみます。
◆海外出張とビザ
皆さんは海外出張や旅行のとき、「ビザ」の申請をしたことはありますか?
おそらく、「ビザ」と言われてもピンと来ない方が多いと思います。
それもそのはず、日本のパスポート(旅券)を持っていると、そもそも海外出張時に「ビザ」を意識する必要がほとんどないのです。
…もっと読む
企業価値と株主価値
企業価値と株主価値はよく使われる言葉ですが、その両者はどのように違うのか考えてみましょう。
貸借対照表の左側は資産であり、資金をどのように運用しているかを表示しています。
資産とは、今後収益を生み出す財産です。
企業は、手持ちの財産をいかに有効に使い、収益を上げるかが問われます。
資産から収益を上げる方法には二つの方法があります。
一つは資産を今の時価で売却してキャッシュに換える …もっと読む
後見人の最後の事務報酬 債務控除の可否
家裁から後見人(保佐人、補助人を含む)に選任されると、後見人は、毎年、家裁に被後見人(被保佐人、被補助人含む)の財産目録を作成し、かつ、後見等(監督)事務報告書を提出することが義務付けられます。
事務報告書には、同意した事項(不動産賃貸借契約、保険金の受取等)や代理した事項(不動産の売買契約、施設への入所契約等)があればその旨も記載します。
◆後見人等の報酬
後見人の報酬については、 …もっと読む
役員変更登記の改正点
少し前になりますが、株式会社の登記手続を定めている商業登記規則の改正で2015年2月から登記実務が一部改正されています。
今後の手続として知っておきたい点について解説します。
◆改正事項
1.役員が新たに就任する場合、本人確認証明書を添付する。
2.代表取締役の辞任届は個人の実印を押印し印鑑証明書添付か会社実印の押印が必要。
3.役員の氏名と共に婚姻前の氏も併せて登記する事ができる …もっと読む
忘年会費用の取り扱い
寒さが本格的になると忘年会の季節です。
仕事がらみの忘年会にもいろいろなパターンがありますが、税務上どのように取り扱われるのでしょうか。
1.全社員を対象として事業所ごとに行われた忘年会
2.一部社員や役員だけで行った忘年会
3.営業部の社員が取引先と行った忘年会
これらに要した費用を会社が負担した場合を見てみます。
◆全社員を対象として行われた忘年会
社員や役員を慰労する為 …もっと読む
年末調整の注意点
今年も年末調整の時期となりましたね。
年末調整と確定申告を混同されている方もおりますので、今回は年末調整について説明したいと思います。
年末調整は、給与の支払を受ける人の一人一人について、原則、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない年税額とを比べて、その過不足を精算する手続きです。
◆今までと比べて変わったところ
…もっと読む