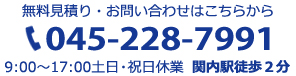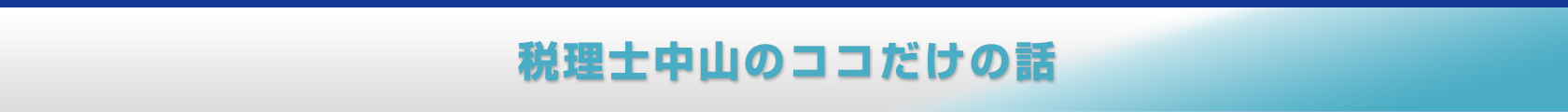おはようございます、最近縁あって子ネコを飼い始めた税理士のなかやまです。
長毛種と手足の短い2匹をお迎えしました。
学生時代にもネコを飼っておりましたが、当時は半家半外でしたが、
最近は厚労省からも室内飼い前提とか。
最近は猛暑のため、御猫様のために24時間エアコン生活になり、
来月の電気代が恐ろしい今日この頃です(汗)。
さて今年も弊所の夏季休暇ですが、事務所全体のお休みはございません。
職員含め交代で休暇を取らせていただきます。
なお8月中旬は税理士不在となりますが、何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
本日は贈与税のハナシです。
生前贈与は相続財産を減らせることに加え、
子や孫の若い世代に相続前から財産を有効に活かしてもらうことができます。
但し、いくつか注意点もありますので、説明いたします。
〇生前贈与加算期間は7年以内に延長
暦年贈与は毎年110万円まで基礎控除を受けられます。
いわゆる、110万円までの贈与は無税というものです。
令和6年1月1日以後の贈与について相続税の課税価格に加算される生前贈与は、
相続開始前7年以内(改正前は3年以内)の贈与となりました。
ただし、令和8年12月31日までの贈与の加算対象期間は3年間に据え置かれ、
以後、毎年1年ずつ延長されて、令和13年1月1日の贈与から7年間となります。
また、延長された4年間に贈与により取得した財産の価額について、
総額100万円まで加算対象外となります。
簡単に言うと、相続直前に贈与を行っても、その分は贈与がなかったもの
(=被相続人の財産)として計算しますよと言うものです。
その期間が3年から7年に延びるのです。
相続対策は直前にやっても効果が薄いので、計画的に行う必要があります。
〇暦年贈与信託を生前贈与に活用
暦年贈与に信託銀行が扱う暦年贈与信託を利用することもできます。
贈与者は金銭信託で委託者兼受益者となり、信託銀行は受託者となって、
毎年、贈与を受ける親族、贈与時期、贈与金額を決めると
信託銀行が贈与の手続きを贈与者、受贈者に取り次いでくれます。
贈与者はあらかじめ贈与したい複数の親族を候補者として選定しておき、
普段は信託財産として運用益を受益者として享受し、
贈与のときは、毎年、候補者の中から贈与したい相手の親族を選び、
贈与したい金額を決めます。
信託銀行は書面で贈与者と受贈者の意思の合致を確認した後、
信託財産から贈与する金額を送金します。
贈与税は基礎控除額110万円を控除した額に課されます。
信託銀行の取扱商品によっては、贈与者が受益者のまま贈与するもの、
贈与時に受益者を受贈者に変更して贈与とするものもあるようです。
「相続」は「争族」と言われるくらい、親兄弟でもトラブルが起きます。
そういった懸念を除くために、遺言や信託などは有効な手段になります。
もっとも費用も掛かりますけど・・・。
〇連年贈与、定額贈与には注意!
暦年贈与で毎年、定額の贈与を継続した場合、贈与額の合計額について課税リスクが生じます。
国税庁は、例示として毎年100万円ずつ10年間の贈与があらかじめ当事者間で約束があり、
贈与が定期金給付契約の締結によるものとされた場合、
契約した年に贈与額全体について贈与税を課すとしています。
暦年贈与信託では、毎年、受贈者を候補者から選定し、贈与の有無、贈与額を決めることができますが、
贈与の際は贈与課税について注意が必要です。
また、贈与には子や孫に資産を早期に移転することで、
その生活スタイルを贈与に依存させてしまう側面もあることにも留意しましょう。
それでは今日はこのへんで。